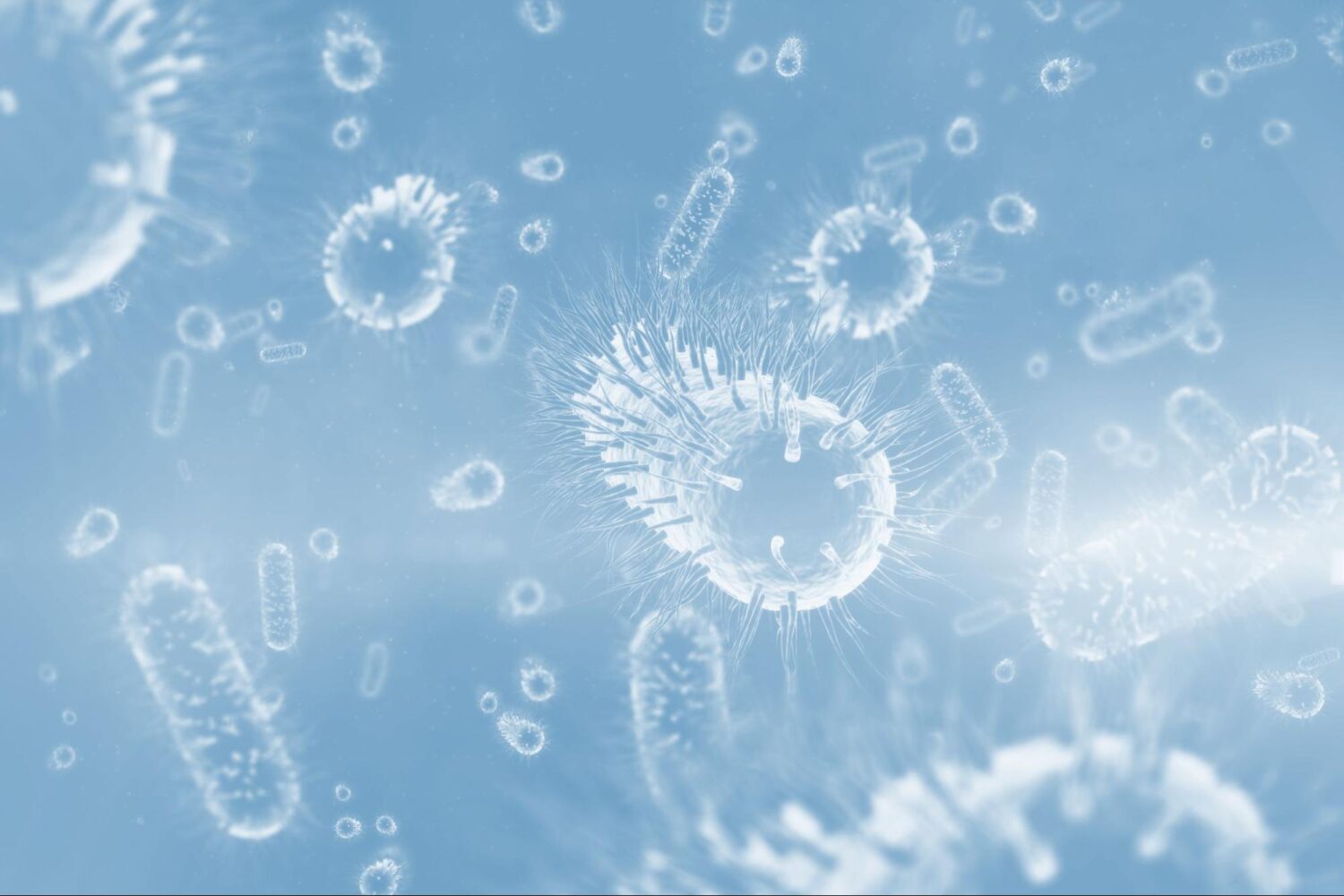マイコプラズマとは
マイコプラズマ感染症は、マイコプラズマ・ニューモニエという細菌によって引き起こされる呼吸器感染症です。この細菌は一般的な細菌とは異なり、細胞壁を持たない特殊な構造をしているため、通常の抗生物質が効きにくく、治療には特定の薬剤が必要になります。
年間を通して発生しますが、特に秋から冬にかけて患者数が増加し、数年ごとに大きな流行を繰り返します。感染者の年齢層は幅広く、小児から高齢者まで全ての年代で発症する可能性があります。
主な感染経路は飛沫感染と接触感染で、感染者の咳やくしゃみによって放出される飛沫を吸い込んだり、ウイルスが付着した手で口や鼻を触ることで感染します。潜伏期間は通常2~3週間と比較的長く、症状が現れない間も他の人への感染力を持っているため、知らないうちに感染を広げてしまう可能性があります。
マイコプラズマの症状
マイコプラズマ感染症の最も特徴的な症状は、長期間続く乾いた咳です。この咳は「乾性咳嗽」と呼ばれ、痰がほとんど出ない点が特徴で、初期は軽い咳でも徐々に激しくなり、夜間に咳込んで眠れないほどになることもあります。
感染初期には発熱、全身のだるさ、頭痛といった風邪に似た症状が現れます。熱は通常38℃前後ですが、時には39℃を超える高熱が出ることもあります。発熱と同時期またはやや遅れて咳が始まり、これが数週間から数ヶ月間続くこともあります。
その他の症状として、のどの痛み、鼻づまり、筋肉痛、関節痛などが現れ、小児では腹痛や下痢、発疹を伴う場合もあります。乳幼児では哺乳力の低下や機嫌の悪さが目立ち、中耳炎を併発することも珍しくありません。
マイコプラズマ肺炎について
マイコプラズマ感染症で特に注意が必要なのがマイコプラズマ肺炎です。マイコプラズマに感染した人の多くは気管支炎ですみますが、一部の人は肺炎に進展することがあります。
一般的な細菌性肺炎では高熱や強い咳、膿性の痰、呼吸困難などの重篤な症状が現れますが、マイコプラズマ肺炎では発熱と乾いた咳が主な症状です。胸部レントゲン検査では肺炎の所見が認められるものの、患者さんの全身状態は比較的良好に保たれています。
ただし、高齢者や基礎疾患をお持ちの方では重症化するリスクがあり、呼吸困難、持続する高熱、強い胸痛、全身状態の悪化などが現れた場合は速やかに医療機関での診察が必要です。
診断と治療
マイコプラズマ感染症の診断は、症状の特徴と検査結果を総合的に判断して行います。迅速診断キットを使用した検査で、のどの奥から採取した検体を用いて短時間で結果を確認できます。血液検査では抗体価を測定し、胸部レントゲン検査で肺炎の有無を確認します。
マイコプラズマは細胞壁を持たない特殊な細菌であるため、通常の風邪薬では効果が期待できません。治療にはマクロライド系、テトラサイクリン系、ニューキノロン系といった特定の抗生物質を使用します。患者さんの年齢や症状の程度、アレルギーの有無などを考慮して最適な薬剤を選択します。
抗生物質の効果は通常、服用開始から2~3日で現れ始めますが、症状が改善しても処方された期間はしっかりと服用を続けることが大切です。対症療法として咳止め薬や解熱鎮痛薬も併用し、十分な水分摂取と適度な休息も治癒を促進するために重要です。
予防法
マイコプラズマ感染症に対する特効的なワクチンは存在しないため、予防には日常的な感染対策が重要です。基本的な手洗いやうがいの徹底、マスクの着用などが感染リスクを下げる効果的な方法です。
外出から帰宅した際の手洗いは、石鹸を使って指の間や爪の周りまで丁寧に洗い、アルコール系の手指消毒剤も併用するとより効果的です。人混みを避け、換気の良い環境を心がけ、体調管理に注意することも大切です。
学校や職場などの集団生活の場では、咳や発熱などの症状がある場合は無理をせず休養を取り、症状が改善するまでは他の人との接触を控えることが感染拡大防止につながります。
当クリニックでのマイコプラズマの診療
当クリニックでは、マイコプラズマ感染症の診断から治療まで、患者さん一人ひとりの状態に応じた医療を提供しています。症状の詳しい聞き取りと身体診察から始まり、必要に応じて迅速診断キット、血液検査、胸部レントゲン検査などを実施し、検査結果と症状を総合的に評価して正確な診断に努めています。
診断が確定した場合は、患者さんの年齢や症状の程度に応じて最適な治療方針を立て、抗生物質の選択から服用方法まで、わかりやすく説明いたします。治療中の経過観察も重要視し、症状の改善具合を定期的に確認して必要に応じて治療方針の調整を行います。
2週間以上続く乾いた咳がある方、微熱が長期間続いている方、家族や職場でマイコプラズマ感染症の診断を受けた方がいる場合、風邪薬を服用しても症状が改善しない方は、お気軽に当クリニックにご相談ください。適切な診断と治療により、症状の早期改善と感染拡大の防止に努めています。