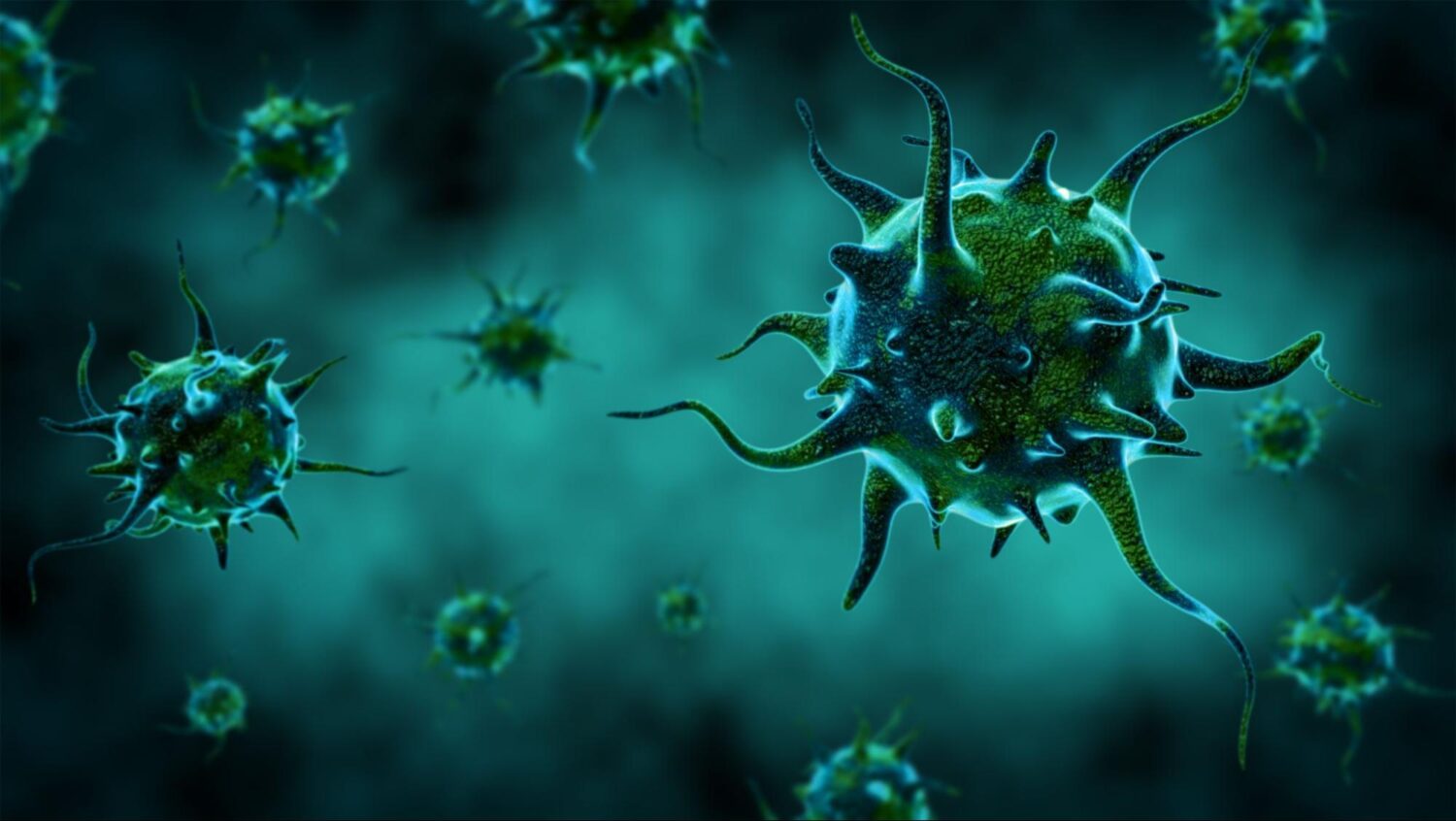ヘルパンギーナとは
ヘルパンギーナとは、コクサッキーウイルス、エコーウイルスなどによって引き起こされる感染症です。主に夏季から秋にかけて流行し、特に未就学児の間で多く見られます。集団保育施設などで集団発生することもあります。
ウイルスは主に次の経路で感染します。飛沫感染は感染者のくしゃみや咳などを通じて広がります。接触感染は感染者の唾液や便などが付着したものを触った後に、口や鼻を触ることで感染します。また、経口感染は汚染された食べ物や飲み物を摂取することでも起こり得ます。
感染力は比較的強く、家族内での二次感染も珍しくありません。潜伏期間は通常3~5日程度で、この間にもウイルスを排出している可能性があります。
ヘルパンギーナの症状と経過
ヘルパンギーナは特徴的な症状があり、早期発見が可能です。
以下のような症状が見られた場合は注意が必要です。
主な症状
突然の高熱が特徴的で、38~40度の発熱が見られます。多くの場合、2~4日間続きますが、解熱後も数日間は体調不良が続くことがあります。のどの奥に小さな水疱や潰瘍がx現れるのが特徴です。これらは直径2~4mm程度の白っぽい水疱として始まり、やがて赤い縁取りのある浅い潰瘍となります。
のどの痛みは特に飲食時に強く現れ、お子さんが食事や水分を取りたがらない原因となります。また、頭痛や腹痛、嘔吐、下痢などの消化器症状を伴うこともあります。
経過と回復
症状は通常3~7日程度で自然に軽快します。ただし、解熱後も喉の痛みが数日間続くことがあります。多くの場合、合併症なく回復しますが、まれに脱水症状や髄膜炎などの合併症を引き起こすことがあります。
お子さんの場合、特に痛みのために水分摂取を拒否することがあり、脱水に注意が必要です。水分摂取量が減少し、尿量が減る、元気がない、皮膚や唇が乾燥するなどの症状がみられた場合は医師に相談してください。
診断方法について
ヘルパンギーナの診断は、主に以下の方法で行われます。
問診と視診
医師が症状や経過について詳しく聞き取りを行い、特に口腔内やのどの奥の状態を丁寧に観察します。ヘルパンギーナに特徴的な水疱や潰瘍の有無、分布を確認します。
血液検査
必要に応じて血液検査を行い、炎症反応や白血球の状態を調べることがあります。ただし、ヘルパンギーナに特異的な検査所見はなく、あくまで合併症の有無や他の疾患との鑑別のために行われます。
鑑別診断
のどに症状が出る他の疾患(溶連菌感染症、手足口病、咽頭結膜熱など)との区別が重要です。症状の特徴や発疹の有無などから総合的に判断します。
医師の診察により、口内の特徴的な病変と臨床症状から診断が可能なケースが多いです。当院では丁寧な問診と診察を行い、適切な診断に努めています。
治療法と家庭での対応
ヘルパンギーナに特効薬はなく、対症療法が中心となります。当院ではお子さんの状態に合わせた治療を提案しています。
解熱鎮痛剤は発熱や痛みを和らげるために処方されることがあります。ただし、使用には適切な用量と間隔を守ることが重要です。喉の痛みを和らげるための局所麻酔薬を含むうがい薬や飲み薬を処方することもあります。
症状が重い場合や脱水症状がある場合は、点滴による水分・電解質の補給を行うことがあります。特に幼いお子さんで水分摂取が難しい場合には有効です。
家庭でのケア
水分補給は最も重要なケアの一つです。喉の痛みがあるため、冷たい飲み物やアイスなどを少量ずつ頻回に与えるとよいでしょう。食事は無理に摂らせる必要はなく、お子さんの食べたいものを少量ずつ与えましょう。柔らかく冷たい食べ物が食べやすいことが多いです。
部屋の湿度を適切に保ち、安静に過ごせる環境を整えましょう。体温管理も大切で、高熱時は冷却シートなどを利用し、室温も調整しましょう。ただし、震えるほど冷やすことは避けてください。
予防法と日常生活での注意点
ヘルパンギーナの予防には、基本的な衛生管理が重要です。
有効な予防策
手洗いはウイルス感染予防の基本です。外出後や食事前、トイレの後などにはしっかりと石けんで手を洗いましょう。うがいも有効で、外出後には口腔内のウイルスを減らすために行うとよいでしょう。
タオルや食器の共用は避け、特に感染者が使用したものは分けて使用し、しっかり洗浄してください。感染者のいる環境では、頻繁に換気を行い、共用部分(ドアノブ、リモコンなど)の消毒も効果的です。
集団生活での注意
保育園や幼稚園など集団生活の場での感染拡大を防ぐため、発症した場合は解熱後24〜48時間経過し、全身状態が良好になるまでは登園を控えることが望ましいです。施設側も日常的な消毒や手洗い指導、体調不良児の早期発見に努めることが重要です。