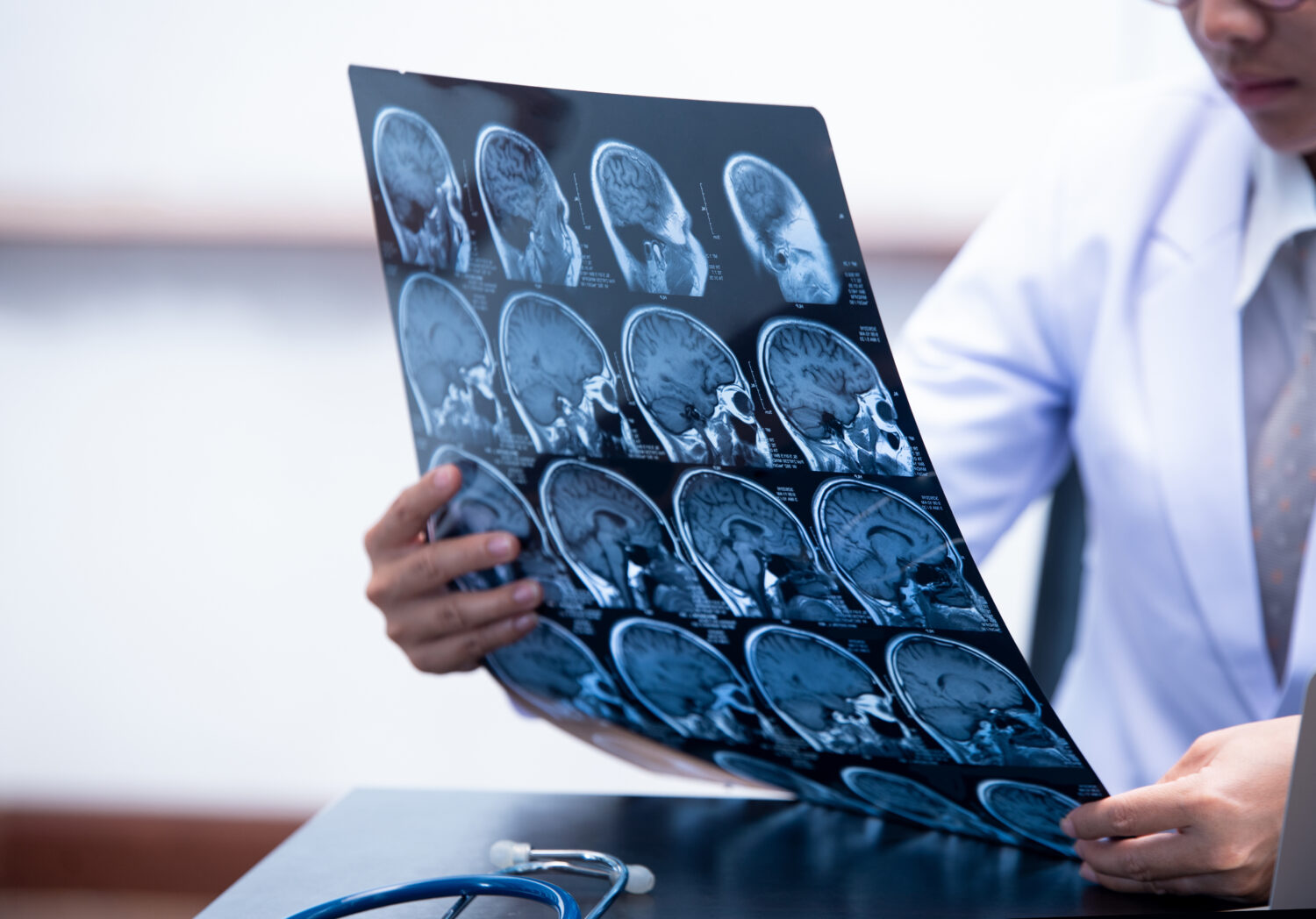脳梗塞は、脳の血管が詰まって血流が止まり、脳の組織が壊死してしまう病気です。突然手足に力が入らなくなったり、言葉が出なくなったり、意識がもうろうとしたりする症状が現れます。高齢者に多く見られますが、働き盛りの方でも発症する病気です。片麻痺、言語障害、意識障害といった症状が急に現れた方、顔や手足のしびれが続いている方は、脳梗塞の可能性があります。こちらでは脳梗塞の症状や治療、予防について詳しくお伝えいたします。
脳梗塞について
脳梗塞は、脳に血液を送る血管が閉塞し、血流が途絶えることにより発症する病気です。血管が詰まると、その先の脳の組織に酸素や栄養が届かなくなり、脳の細胞が壊死してしまいます。一度壊死した脳の細胞は元に戻らないため、早期の治療が極めて大切になります。
脳梗塞にはいくつかのタイプがあります。一番多いのは血管の動脈硬化が進んで血管が狭くなったり詰まったりする「アテローム性血栓性脳梗塞」で、全体の約6割を占めます。次に多いのが心臓でできた血の塊が脳の血管に飛んで詰まる「心原生脳塞栓」で、約3割です。残りは細い血管が詰まる「ラクナ梗塞」となります。
脳梗塞になりやすいのは65歳以上の高齢者ですが、最近では50代、40代の方にも見られるようになってきました。男性の方が女性より多く発症しますが、高齢になると男女差は小さくなります。夏の暑い時期や冬の寒い時期に多く起こる傾向があり、これは脱水や血圧の変動が関係していると考えられています。
脳梗塞の前兆として、一時的に症状が現れてすぐに良くなる「一過性脳虚血発作」があります。これは「脳梗塞の警告信号」とも呼ばれ、この段階で適切な治療を受けることで、本格的な脳梗塞を防ぐことができる場合があります。
脳梗塞の症状
脳梗塞の症状は、詰まった血管の場所や範囲によって様々です。症状は突然現れることが多く、時間が経つにつれて悪化することもあります。家族や周りの人が気づきやすい症状もあるので、早期発見のために知っておくことが大切です。
運動麻痺
一番よく見られる症状は、体の片側の手足に力が入らなくなることです。右脳に梗塞が起こると左半身に、左脳に梗塞が起こると右半身に麻痺が現れます。軽い場合は「なんとなく力が入りにくい」程度ですが、重い場合は全く動かなくなってしまいます。
手の麻痺では、物を持てなくなったり、箸が使えなくなったりします。足の麻痺では、歩けなくなったり、立っていられなくなったりします。顔の麻痺が起こると、口角が下がって表情が歪んだり、よだれが出たりすることもあります。
言語障害
言葉に関する症状も脳梗塞でよく見られます。聞いた言葉は理解できるが話す能力が低下した「運動性失語症」、話を聞いても理解することができなくなる「感覚性失語症」、ろれつが回らなくなる「構音障害」などがあります。
軽い場合は「少し話しにくい」程度ですが、重い場合は全く話せなくなったり、相手の話が全く理解できなくなったりします。文字を読んだり書いたりすることも難しくなることがあります。
意識障害
脳梗塞の範囲が広い場合や、大切な部分に起こった場合は、意識レベルが下がることがあります。軽い場合はぼんやりとした状態になり、重い場合は昏睡状態になることもあります。
意識がはっきりしていても、時間や場所がわからなくなったり、家族の顔がわからなくなったりすることもあります。また集中力が続かなくなったり、物事を覚えられなくなったりすることもあります。
その他の症状
脳梗塞では他にも様々な症状が現れることがあります。めまい、吐き気、頭痛、視野の異常、物が二重に見える、バランスが取れなくなる、手足のしびれなどです。これらの症状が単独で現れることもあれば、いくつか組み合わさって現れることもあります。
症状の程度は人それぞれで、軽微な症状から重篤な症状まで幅があります。軽い症状でも「おかしいな」と思ったら、早めに医療機関を受診することが大切です。
脳梗塞の診断
脳梗塞の診断では、症状の現れ方と画像検査が重要になります。当クリニックでは、患者さんやご家族から症状の経過を詳しくお聞きし、神経学的な診察を行います。その上で必要な検査を行い、正確な診断をするよう努めています。
画像検査では、CTスキャンやMRI検査を行います。CTスキャンは比較的短時間で撮影でき、脳出血との区別をつけるのに役立ちます。MRI検査はより詳しく脳の状態を調べることができ、小さな梗塞や早期の梗塞も発見できます。
血液検査では、炎症の程度や血糖値、コレステロール値などを調べます。心電図検査では、心房細動などの不整脈がないかを確認します。これらの検査結果を総合して、脳梗塞のタイプや原因を特定します。
脳梗塞が疑われる場合は、できるだけ早く専門的な検査と治療が受けられる医療機関への紹介を行います。「時間との勝負」という側面があるため、迅速な対応を心がけています。
脳梗塞の治療
脳梗塞の治療は、急性期の治療と慢性期の治療に分かれます。急性期では詰まった血管を早く開通させることが大切で、慢性期では再発防止と機能回復が主な目標になります。
急性期の治療
脳梗塞を起こしてから数時間以内であれば、血栓を溶かす薬(t-PA)を使った治療が可能な場合があります。この治療により、詰まった血管を再開通させ、脳のダメージを最小限に抑えることができます。ただしこの治療には時間制限があり、症状が出てから4.5時間以内に開始する必要があります。
最近では、カテーテルを使って直接血栓を取り除く「血管内治療」も行われるようになりました。これらの治療は専門的な設備と技術が必要なため、該当する患者さんには速やかに専門医療機関への紹介を行います。
慢性期の治療
急性期を過ぎると、再発防止のための治療が中心になります。血液をサラサラにする薬(抗血小板薬や抗凝固薬)を使って、新たな血栓ができるのを防ぎます。また血圧、血糖値、コレステロール値などをしっかりコントロールすることも大切です。
リハビリテーションも治療の重要な柱です。理学療法、作業療法、言語療法などを通じて、失われた機能の回復を目指します。リハビリは早期に始めるほど効果が高いとされており、患者さんの状態に応じて適切なリハビリ施設への紹介も行います。
脳梗塞の予防
脳梗塞は予防できる病気です。生活習慣を改善し、危険因子をコントロールすることで、発症リスクを大幅に下げることができます。特に高血圧、糖尿病、脂質異常症、心房細動などがある方は、しっかりとした管理が必要です。
生活習慣の改善
食事では、塩分を控えめにし、野菜や魚を多く取るようにします。動物性脂肪を控え、植物性の油を使うことも大切です。禁煙は脳梗塞予防の最も重要な要素の一つで、喫煙している方は是非禁煙に取り組んでください。
適度な運動も効果的で、週に3~4回、30分程度のウォーキングなどの有酸素運動がお勧めです。激しい運動は必要なく、無理のない範囲で続けることが大切です。
十分な水分摂取も重要です。特に夏場や入浴後、起床時などは脱水になりやすいので、こまめに水分を取るよう心がけてください。アルコールは適量にとどめ、過度の飲酒は控えましょう。
定期的な健康管理
血圧、血糖値、コレステロール値の定期的なチェックが大切です。これらの数値が高い場合は、薬による治療も含めてしっかりとコントロールする必要があります。心房細動などの不整脈がある場合は、血栓予防のための薬物治療が必要になることもあります。
定期的な健康診断を受け、異常が見つかったら早めに治療を開始することが、脳梗塞の予防につながります。また、一過性脳虚血発作などの前兆症状が現れた場合は、速やかに医療機関を受診することが大切です。
脳梗塞後の生活
脳梗塞を起こした後の生活では、再発防止と残った機能を最大限活用することが大切になります。多くの方がある程度の後遺症を抱えながらも、適切なサポートにより充実した生活を送っています。
薬の服用は継続することが重要で、自己判断で中止せず、定期的に医師の診察を受けながら調整していきます。血圧や血糖値の管理も続ける必要があり、家庭での測定も役立ちます。
リハビリは退院後も継続することが大切です。通院でのリハビリや、訪問リハビリ、デイサービスなど、患者さんの状態に応じて様々な選択肢があります。また、家族の方の理解とサポートも回復には欠かせません。
緊急時の対応
脳梗塞では、以下のような症状が現れた場合は緊急事態です。片側の手足に急に力が入らなくなった、急に言葉が出なくなったりろれつが回らなくなった、急に意識がもうろうとした、急に激しい頭痛が起こった、急にめまいやふらつきが起こって立っていられなくなったなどの症状です。
このような症状が現れたら、すぐに救急車を呼んでください。「様子を見よう」と思わず、迷わず119番通報することが大切です。早期の治療により、後遺症を軽くしたり、命を救ったりすることができます。
当クリニックでの脳梗塞の診療
当クリニックでは、脳梗塞の早期発見から予防、慢性期の管理まで、幅広い医療サービスを提供しています。脳梗塞が疑われる症状の方には、迅速な診断と適切な医療機関への紹介を行います。
脳梗塞の危険因子となる高血圧、糖尿病、脂質異常症、心房細動などの管理にも力を入れています。定期的な検査により、これらの疾患を早期に発見し、適切な治療を行うことで脳梗塞の予防に努めています。
また、脳梗塞を起こした後の患者さんの長期管理も行っています。再発防止のための薬物治療、生活指導、定期的な検査を通じて、患者さんとご家族をサポートいたします。リハビリ施設や介護サービスとの連携も大切にしており、患者さんが安心して生活できるよう総合的な支援を行っています。