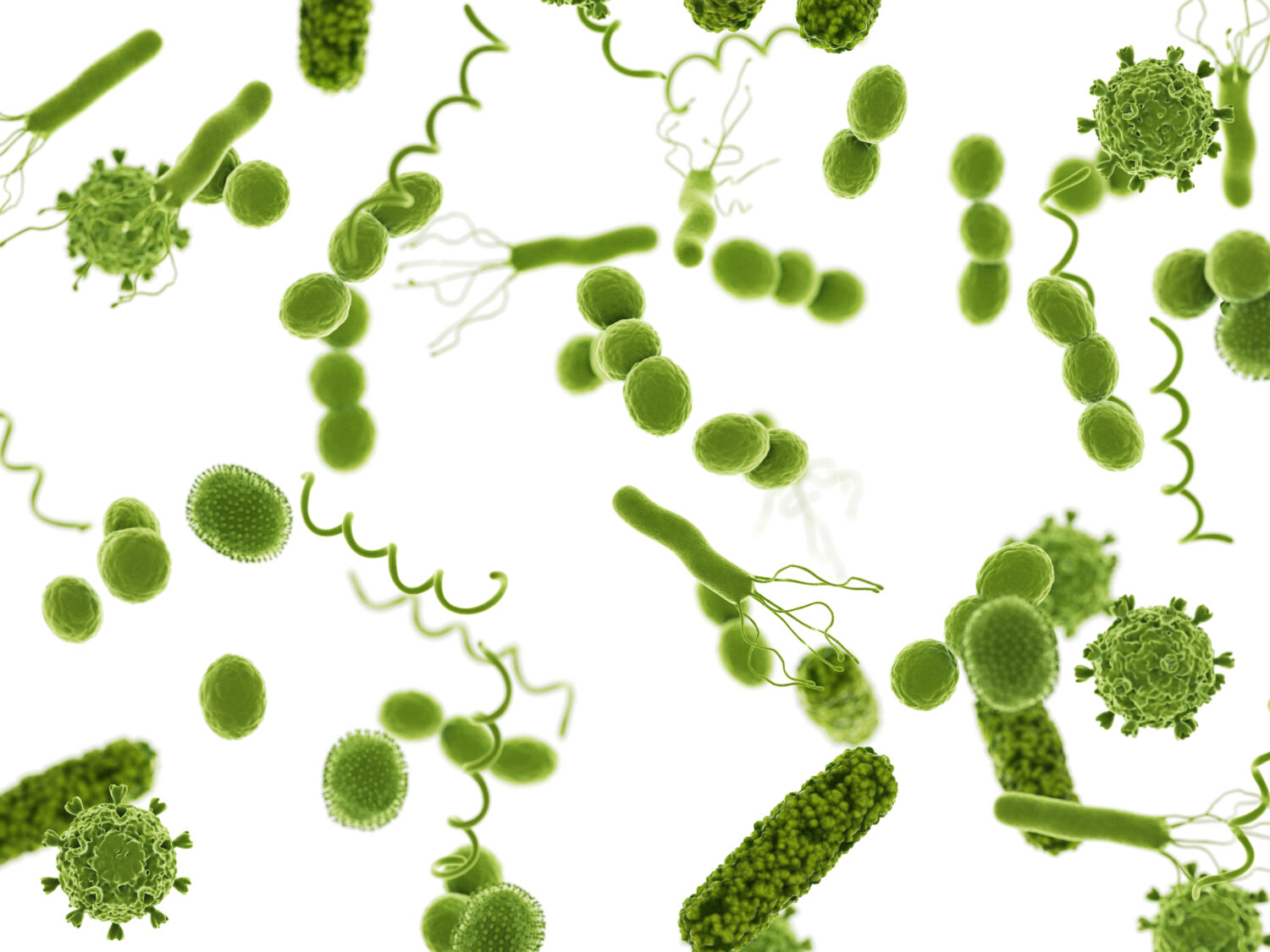C型肝炎について
C型肝炎は、C型肝炎ウイルス(HCV)の感染により肝臓に炎症が起こる病気です。主に血液を介して感染し、慢性化して肝硬変や肝がんに進行するリスクがあります。かつては「治らない病気」とされていましたが、現在では飲み薬だけで95%以上の方が完治できるようになりました。
C型肝炎ウイルスは感染力はB型肝炎ウイルスほど強くありませんが、一度感染すると約70%の方が慢性感染に移行します。慢性感染になると、ウイルスは肝臓に住み続けて徐々に肝臓の細胞を破壊していき、放置すると20~30年で肝硬変に、さらに肝がんに進行することがあります。
日本では約100万人の方がC型肝炎ウイルスに感染していると推定されています。日本では1960~1980年代の輸血や血液製剤による感染が多く、現在の感染者の多くは中高年の方です。
C型肝炎の感染経路
C型肝炎ウイルスは主に血液を介して感染します。感染力はB型肝炎ほど強くありませんが、血液が関わる場面では注意が必要です。現在では新たな感染は減少していますが、過去の医療行為による感染が問題となっています。
輸血・血液製剤による感染
1992年以前の輸血や血液製剤の使用が、日本でのC型肝炎感染の最も大きな原因でした。当時はまだウイルスの検査体制が不十分で、感染した血液が輸血に使用されることがありました。現在では厳格な検査により、輸血による感染はほぼゼロになっています。
医療機器による感染
注射針や内視鏡、手術器具などの医療機器の消毒が不十分だった場合に感染することがあります。現在では使い捨て器具の使用や厳格な消毒により、医療機関での感染はほとんどありません。
しかし、過去には注射針の使い回しや消毒不十分な器具の使用により感染が起こることがありました。特に集団予防接種での注射針の連続使用は、感染拡大の原因の一つとされています。
その他の感染経路
入れ墨(刺青)、ピアスの穴開け、鍼治療などで使用される器具が適切に消毒されていない場合に感染することがあります。これらの処置を受ける場合は、使い捨て器具を使用するか、適切な消毒を行っている信頼できる施設を選ぶことが大切です。
薬物使用時の注射器の共用も感染リスクが高く、海外では重要な感染経路となっています。また、歯ブラシやカミソリなどの血液が付着する可能性のある日用品の共用でも、まれに感染することがあります。
性行為による感染は、B型肝炎に比べると非常に少ないとされていますが、複数のパートナーとの性行為や、HIVとの重複感染がある場合はリスクが高まります。
母子感染も可能性はありますが、B型肝炎に比べると頻度は低く(約5~10%)、現在のところ有効な予防法がないのが現状です。
C型肝炎の症状
急性期の症状
感染直後の急性期では、全身倦怠感、食欲不振、吐き気、腹部不快感などの軽い症状が出ることがあります。まれに黄疸が現れることもありますが、多くの場合は風邪程度の軽い症状で、C型肝炎の感染に気づかないことが多いです。
急性期の症状は自然に改善することが多いですが、ウイルスが完全に排除されることは少なく、約70%の方が慢性感染に移行します。
慢性期の症状
慢性期でも、多くの場合は無症状で経過します。症状があっても、軽い倦怠感、疲れやすさなどで、日常生活に大きな支障をきたすことは少ないです。そのため、「調子が悪いのは年のせい」「疲れているだけ」と思って見過ごしてしまうことがあります。特徴的な症状がないため、他の病気の検査・治療の最中に偶発的に感染を指摘されることがあります。
進行期の症状
慢性肝炎から肝硬変に進行すると、様々な症状が現れるようになります。腹水によりお腹が張る、足のむくみ、食道静脈瘤の破裂による吐血、肝性脳症による意識障害などが起こることがあります。また、黄疸により皮膚や白目が黄色くなることもあります。
肝がんが発生した場合は、腹痛、体重減少、食欲不振などの症状が現れることがありますが、初期には症状がないことも多く、定期的な検査による早期発見が重要です。
C型肝炎の診断
C型肝炎の診断は血液検査により行います。ウイルスの有無、感染の活動性、肝臓の状態などを詳しく調べることで、適切な治療方針を決定します。
HCV抗体検査は、C型肝炎ウイルスに対する抗体があるかどうかを調べる検査です。陽性の場合は現在感染しているか、過去に感染したことがあることを示します。
HCV抗体検査が陽性の場合、HCV-RNA定量検査を行います。HCV-RNA定量検査は、血液中のウイルス量を測定する検査で、現在ウイルスに感染しているかどうかを判定できます。この検査が陽性であれば現在の感染を示し治療の対象となります。検出感度以下の場合は、ウイルスは体内から排除されている状態です。
ウイルス遺伝子型(ジェノタイプ)の検査も重要で、治療薬の選択に必要です。日本では1型と2型が多く、それぞれに適した治療薬があります。
肝機能検査(ALT、AST、ビリルビンなど)により肝臓の炎症や機能の程度を評価し、画像検査(超音波、CT、MRIなど)により肝臓の形態や腫瘍の有無を調べます。肝硬変の程度を正確に評価するために、肝生検を行うこともあります。
C型肝炎の治療
C型肝炎の治療は劇的に進歩し、現在では飲み薬だけで95%以上の方が完治できるようになりました。治療期間も短く、副作用も軽微で、多くの患者さんにとって希望の光となっています。
直接作用型抗ウイルス薬(DAA)
現在の標準治療は直接作用型抗ウイルス薬(DAA)による治療です。これらの薬はウイルスの増殖に必要な酵素を直接阻害することで、ウイルスを排除します。代表的な薬剤には、ハーボニー、マヴィレット、エプクルーサなどがあります。
治療成功率(SVR:持続的ウイルス学的著効)は95%以上と非常に高く、副作用も軽微で日常生活に大きな支障をきたすことはほとんどありません。
治療後の管理
C型肝炎が治癒した後も、定期的な経過観察が重要です。ウイルスが排除されても、すでに起こってしまった肝臓の線維化は完全には元に戻らないため、肝硬変や肝がんのリスクが残ります。
定期的な血液検査、腫瘍マーカー検査、画像検査により、肝硬変の程度の評価や肝がんの早期発見に努めます。
また、他の原因による肝障害を防ぐため、アルコールや薬剤による肝障害を避けることも重要です。
C型肝炎の予防
C型肝炎にはワクチンがないため、予防は感染経路を断つことが中心となります。血液との接触を避けることが最も重要で、日常生活でのちょっとした注意により感染を防ぐことができます。
個人使用物品(歯ブラシ、カミソリ、爪切りなど)は共用せず、個人専用のものを使用します。これらの器具には血液が付着する可能性があるため、家族間でも共用は避けましょう。
医療機関での処置、歯科治療、刺青、ピアスなどを受ける場合は、使い捨て器具を使用するか、適切な消毒を行っている信頼できる施設を選びます。施術前に感染対策について確認することも大切です。
薬物の注射器共用は絶対に避けるべきで、海外では重要な感染経路となっています。また、性行為による感染リスクは低いものの、複数のパートナーとの性行為や出血を伴う可能性のある行為では注意が必要です。
当クリニックでのC型肝炎の診療
当クリニックでは、C型肝炎の検査から治療法の提案、治癒後の長期フォローまで、患者さんお一人おひとりの状況に応じた包括的な医療を提供しています。初回の血液検査により感染の有無と肝臓の状態を詳しく評価し、治療の必要性を判断いたします。
直接作用型抗ウイルス薬治療、肝硬変や肝がんなど専門的な治療が必要な場合は、信頼できる専門医療機関への紹介を行い、患者さんが最適な医療を受けられるよう連携を図ります。
治癒後も定期的な血液検査や画像検査、服薬治療を継続し、肝機能の維持、肝がんの早期発見などに努めます。
また、家族の方への検査の勧奨や予防指導も行い、感染拡大の防止に努めています。患者さんのプライバシーを最大限尊重しながら、必要な情報提供とサポートを行います。
直接作用型抗ウイルス薬治療、肝硬変や肝がんなど専門的な治療が必要な場合は、信頼できる専門医療機関への紹介を行い、患者さんが最適な医療を受けられるよう連携を図ります。