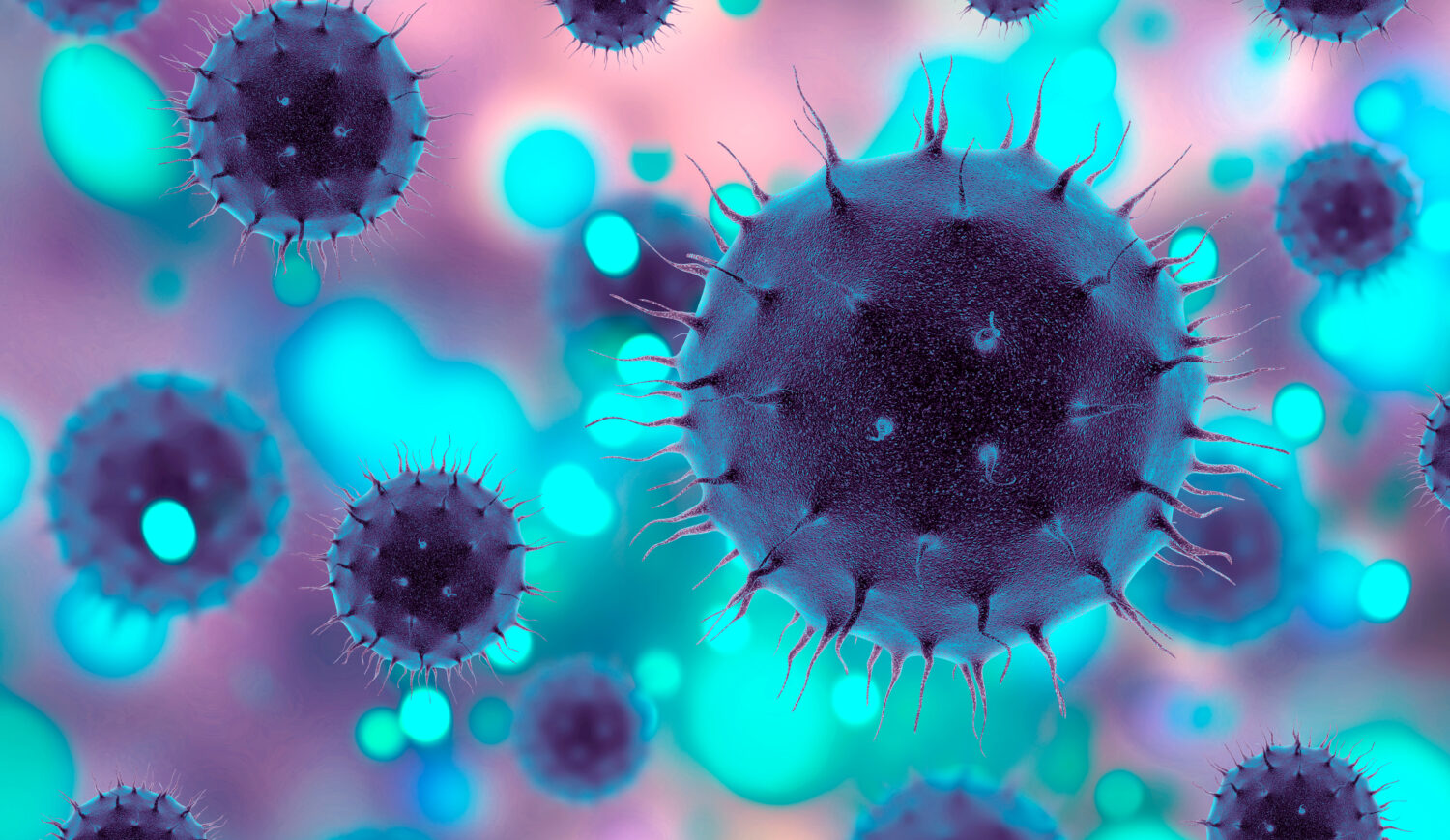細菌性腸炎について
細菌性腸炎は、様々な病原細菌が腸管に感染することで起こる急性の感染症です。これらの細菌は腸の粘膜に付着して毒素を出したり、直接腸の組織を傷つけたりすることで、下痢や腹痛などの症状を引き起こします。
細菌性腸炎の多くは食中毒として起こり、汚染された食品や水を摂取することで感染します。夏場の気温が高い時期に多く見られますが、最近では食品の流通や調理環境の変化により、年間を通して発生しています。
症状の現れ方は原因となる細菌によって異なりますが、多くの場合は食事から数時間から数日後に急激に症状が現れます。軽症例では自然に治ることもありますが、重症例では入院治療が必要になることもあります。
日本では年間数万件の細菌性腸炎の報告があり、特に集団食中毒として社会問題となることもあります。適切な食品管理と早期の診断・治療により、多くの場合は良好な経過をたどります。
細菌性腸炎の原因菌
細菌性腸炎を起こす主な細菌には、それぞれ特徴的な感染源や症状があります。日本で多く見られる代表的な細菌について詳しく説明します。
サルモネラ菌
サルモネラ菌は食中毒の代表的な原因菌の一つで、卵や鶏肉、豚肉などに多く見られます。特に卵を使った料理(生卵、半熟卵、卵を使ったケーキなど)や、十分に加熱されていない鶏肉料理で感染することがよくあります。
サルモネラによる腸炎では、食事から12~72時間後に症状が現れ、激しい腹痛、下痢、発熱、嘔吐が起こります。下痢は水様便から始まり、血液が混じることもあります。発熱は38~40℃の高熱になることが多いです。
カンピロバクター菌
カンピロバクター菌は、鶏肉に最も多く見られる細菌で、生や加熱不十分な鶏肉料理(鶏刺し、鶏たたき、焼き鳥など)が主な感染源です。また、牛や豚などの食肉からの感染もあります。
潜伏期間は1~7日と長く、症状は腹痛、下痢、発熱で始まります。特に腹痛が激しいのが特徴で、下痢は水様便から血便まで様々です。症状は1週間程度続くことが多く、まれに手足の麻痺を起こすギラン・バレー症候群という合併症を起こすことがあります。
病原性大腸菌
病原性大腸菌にはいくつかの種類があり、その中でも腸管出血性大腸菌(O157など)は特に危険です。牛肉、特にひき肉を使った料理や、生野菜、井戸水などから感染することがあります。
症状は激しい腹痛と血便が特徴的で、発熱はそれほど高くないことが多いです。重症例では溶血性尿毒症症候群(HUS)や急性脳症などの重篤な合併症を起こすことがあり、特に小児や高齢者では注意が必要です。
その他の原因菌
腸炎ビブリオは海産物(特に魚介類の刺身)から感染し、夏場に多く見られます。黄色ブドウ球菌は調理者の手から食品に移って増殖し、毒素を作ることで食中毒を起こします。ウェルシュ菌は大量調理した食品(カレー、シチューなど)で増殖しやすく、集団食中毒の原因となることがあります。
細菌性腸炎の症状
細菌性腸炎の症状は原因菌や感染の程度によって異なりますが、多くの場合は急激に症状が現れるのが特徴です。主な症状は消化器症状と全身症状に分けられます。
消化器症状
下痢は最も多く見られる症状で、1日に数回から十数回の頻回な排便があります。初期は水様便であることが多く、徐々に粘液便や血便に変わることもあります。便の量は多く、時には「水のような便」と表現されるほど液状になります。
腹痛も重要な症状で、下腹部を中心とした痛みが多く見られます。痛みは持続的な鈍痛から、間欠的な激痛まで様々で、排便前に強くなり、排便後に軽くなることが特徴的です。
嘔吐は病気の初期に現れやすく、食事や水分摂取により誘発されることがあります。激しい嘔吐により脱水を起こしやすくなるため注意が必要です。
腹部膨満感や腸蠕動音の亢進(お腹がゴロゴロ鳴る)も見られることがあります。また、食欲不振は症状が続く間は持続的に見られます。
全身症状
発熱は多くの細菌性腸炎で見られ、38℃以上の高熱になることが多いです。熱の程度は原因菌により異なり、サルモネラでは高熱、カンピロバクターでは中等度の発熱、腸管出血性大腸菌では軽度の発熱または無熱のことが多いです。
全身倦怠感、頭痛、筋肉痛なども現れることがあり、これらは発熱や脱水に伴って起こることが多いです。脱水が進むと、口の渇き、尿量減少、皮膚の弾力性低下などの症状も現れます。
重症例の症状
重症例では、脱水による血圧低下、頻脈、意識レベルの低下などが現れることがあります。また、敗血症を起こした場合は、ショック状態や多臓器不全に至ることもあり、緊急治療が必要になります。
腸管出血性大腸菌による感染では、溶血性尿毒症症候群(HUS)により腎機能障害や意識障害を起こすことがあり、特に注意が必要です。
細菌性腸炎の診断
細菌性腸炎の診断は、症状の特徴と検査結果を総合して行います。当クリニックでは、患者さんの症状を詳しくお聞きし、適切な検査により正確な診断を行います。
問診では、症状の経過、食事歴、同じものを食べた人の症状の有無、海外渡航歴などを詳しくお聞きします。特に発症前72時間以内の食事内容は重要な情報で、感染源の特定に役立ちます。
便培養検査は診断の要となる検査で、原因菌を特定し、適切な治療薬の選択が可能になります。ただし、結果が出るまでに数日かかるため、重症例では検査結果を待たずに治療を開始することもあります。
血液検査では、白血球数の増加、炎症反応(CRP)の上昇、脱水の程度などを評価します。重症例では、腎機能や肝機能、電解質バランスなども詳しく調べます。
細菌性腸炎の治療
細菌性腸炎の治療は、脱水の補正と症状の緩和が中心となります。多くの場合は対症療法で改善しますが、重症例や特定の細菌による感染では抗生物質治療が必要になることもあります。
水分・電解質の補給
脱水の予防と改善が最も重要な治療です。軽症例では経口補水液による水分補給を行います。市販の経口補水液や、薄めたスポーツドリンクを少量ずつ頻回に摂取します。一度に大量を飲むと嘔吐を誘発するため、5~10分おきに少しずつ飲むことがポイントです。
中等症以上や経口摂取が困難な場合は、点滴による水分補給を行います。電解質バランスの調整も同時に行い、脱水の改善を図ります。
症状に対する治療
下痢に対しては、基本的には止痢薬は使用しません。下痢は体内の細菌や毒素を排出する防御反応であるため、むやみに止めると病原体の排出が遅れ、症状が長引くことがあります。
腹痛に対しては、鎮痛薬や鎮痙薬を適切に使用します。発熱に対しては解熱薬を使用しますが、高熱でなければ無理に下げる必要はありません。
吐き気や嘔吐が強い場合は、制吐薬を使用することもあります。ただし、薬物療法よりも安静と水分補給が重要です。
整腸剤の投与により、腸内細菌叢のバランスを整え細菌の排出を促進します。症状が重い場合やリスクの高い患者さんには抗生物質を使用することがあります。
合併症と注意点
細菌性腸炎では、適切な治療を行わないと様々な合併症を起こすリスクがあります。最も多いのは脱水症状で、特に小児や高齢者では重篤になりやすいため注意が必要です。
敗血症は、細菌が血液中に入り込んで全身に広がった状態で、高熱、血圧低下、意識障害などを起こします。免疫力の低下した方や高齢者で起こりやすく、緊急治療が必要です。
溶血性尿毒症症候群(HUS)は、腸管出血性大腸菌感染症の重篤な合併症で、血小板減少、溶血性貧血、急性腎不全を起こします。特に小児に多く、透析治療が必要になることもあります。
その他の合併症として、反応性関節炎、ギラン・バレー症候群(カンピロバクター感染後)などが報告されています。
細菌性腸炎の予防
細菌性腸炎の予防で最も重要なのは、食品の適切な管理と調理です。「つけない、増やさない、やっつける」という食中毒予防の3原則を守ることが基本になります。
食品の購入と保存
新鮮な食材を選び、購入後は速やかに冷蔵・冷凍保存します。肉類と他の食品は分けて保存し、交差汚染を防ぎます。冷蔵庫の温度は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に保ちます。
賞味期限や消費期限を守り、期限切れの食品は使用しません。冷凍食品の解凍は冷蔵庫内で行い、室温での解凍は避けます。
調理時の注意
調理前後の手洗いを徹底し、調理器具も清潔に保ちます。まな板や包丁は、肉類用と野菜用を分けて使用します。肉類は中心部まで十分に加熱し、75℃以上で1分間以上加熱することが推奨されます。
卵料理では、新鮮な卵を使用し、ひび割れた卵は使わないようにします。生卵や半熟卵は避け、十分に加熱した卵料理を摂取します。
食事時の注意
調理後はできるだけ早く食べ、室温で長時間放置しないようにします。作り置きした料理は冷蔵保存し、食べる前に十分に再加熱します。
外食時は、清潔な店を選び、生や加熱不十分な料理は避けます。特に夏場や衛生状態の良くない場所では注意が必要です。
当クリニックでの診療
当クリニックでは、細菌性腸炎の迅速な診断から適切な治療まで、患者さんの症状に応じた医療を提供しています。急性の下痢や腹痛でお困りの患者さんに対して、詳しい問診と身体診察、必要な検査により正確な診断を行います。
軽症から中等症の患者さんには、外来での点滴治療や内服薬による治療を行います。脱水の程度を注意深く評価し、適切な水分・電解質の補給を行います。症状の経過を定期的に確認し、改善が見られない場合は治療方針を見直します。
重症例や合併症のリスクが高い患者さんには、専門医療機関への紹介を速やかに行います。特に小児や高齢者、免疫力の低下した方では、慎重な対応を心がけています。
また、感染拡大防止のための指導も重要な診療内容です。家庭での隔離方法、手洗いの徹底、食品の適切な管理について具体的にお伝えし、二次感染の予防に努めます。
回復期には、食事の再開方法や再発予防について詳しくご説明し、患者さんが安心して日常生活に戻れるようサポートいたします。