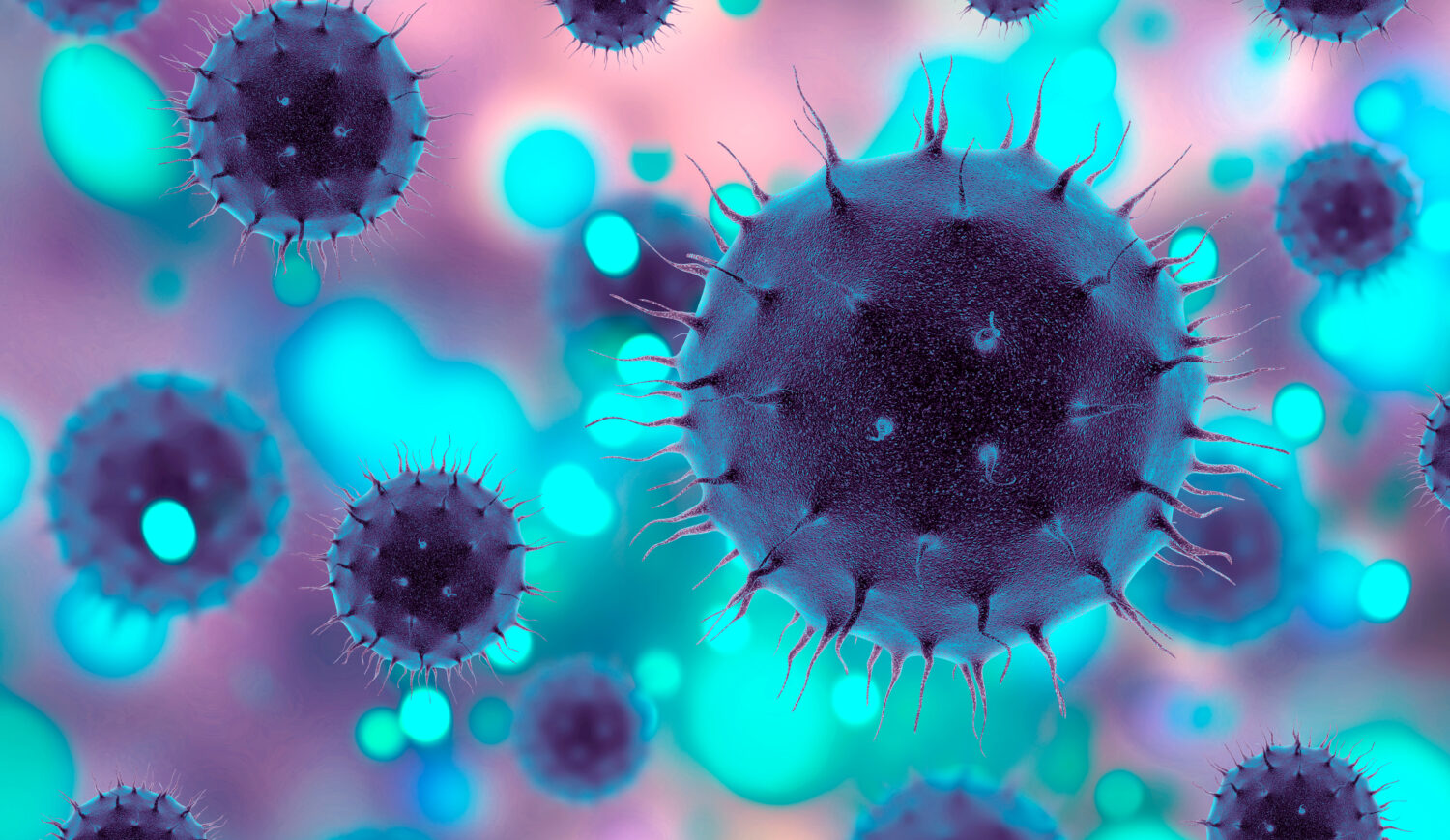ピロリ菌について
ピロリ菌は、正式には「ヘリコバクター・ピロリ」という名前の細菌です。胃の中は強い酸性で、普通の細菌は生きていけませんが、ピロリ菌は特殊な仕組みを持っていて、胃酸の中でも生き続けることができ、一度感染すると治療しない限り一生胃の中に感染しています。
ピロリ菌は1983年にオーストラリアの医師によって発見されました。それまで胃潰瘍や胃炎の原因はストレスや食生活だと考えられていましたが、実はこの細菌が主な原因だったことが分かりました。
日本でのピロリ菌感染率は年代によって大きく異なります。現在の70代以上では70%以上、60代では約60%の方が感染していると言われていますが、若い世代では減少傾向にあります。
ピロリ菌に感染していても、すぐに症状が出るわけではありません。多くの方は何十年もの間、感染に気づかずに過ごします。しかし、その間にも胃の粘膜では慢性的な炎症が続いており、徐々に胃炎が進行していきます。
ピロリ菌の感染経路
ピロリ菌がどのように感染するかは、まだ完全には分かっていません。経口的に体内に入ることによって感染するのではないかと考えられており、胃酸の分泌や免疫機能が十分でない乳幼児期にに感染すると言われています。
水や食べ物を通じた感染が指摘されており、特に衛生環境が良くなかった時代には、汚染された井戸水や生野菜などから感染することがあったようです。現在では上下水道が整備されているため、このような感染はほとんどありません。また、感染している家族が噛み砕いた食べ物を子どもに与えたりすることによる感染も考えられています。大人になってからの日常生活の中では、ピロリ菌の感染はほとんど起こらないと考えられています。
ピロリ菌が引き起こす病気
ピロリ菌感染による最も大きな問題は、様々な胃の病気を引き起こすことです。感染初期には急性胃炎を起こすことがありますが、多くの場合は気づかれずに慢性胃炎に移行します。
慢性胃炎・萎縮性胃炎
ピロリ菌が長期間胃に住みつくと、胃の粘膜に慢性的な炎症が起こります。最初は胃の下部(胃前庭部)から炎症が始まり、徐々に胃全体に広がっていきます。炎症が長く続くと、胃の粘膜が薄くなって萎縮し、萎縮性胃炎という状態になります。
萎縮性胃炎が進むと、胃酸の分泌が減ったり、胃の消化機能が低下したりします。また、この状態は胃がんが起こりやすい土壌となってしまいます。
胃潰瘍・十二指腸潰瘍
ピロリ菌感染者の一部では、胃潰瘍や十二指腸潰瘍を起こします。従来はストレスや食生活が原因と考えられていましたが、実際にはピロリ菌が主な原因であることが分かっています。
胃がん
ピロリ菌感染が引き起こす最も重大な病気が胃がんです。世界保健機関(WHO)では、ピロリ菌を胃がんの確実な発がん因子として認定しています。
ピロリ菌感染により萎縮性胃炎、腸上皮化生、異形成を経て胃がんに至る過程が明らかになっています。感染期間が長いほど、また萎縮の程度が強いほど胃がんのリスクが高くなります。
その他の病気
特発性血小板減少性紫斑病、鉄欠乏性貧血、胃MALTリンパ腫(胃に発生するリンパ腫)、機能性ディスペプシア(検査で明らかな異常が見つからないにもかかわらず胃の不調が続く状態)にもピロリ菌が関与していることがあります。
ピロリ菌の検査方法
ピロリ菌の検査には、内視鏡を使う方法と使わない方法があります。
内視鏡を使わない検査
尿素呼気試験は、最も正確で信頼性の高い検査方法です。検査薬を飲んだ後に息を袋に吹き込むだけの簡単な検査で、痛みもありません。ピロリ菌が持つ酵素の働きを利用した検査で、菌がいれば呼気中に特殊な成分が検出されます。
血液検査では、ピロリ菌に対する抗体を調べます。採血だけで済む簡単な検査ですが、過去の感染歴も反映するため、除菌後の判定には適さないことがあります。
便検査では、便の中のピロリ菌の成分を直接調べる検査で、除菌後の判定にも使えます。
尿検査では、尿中のピロリ菌抗体を検出します。手軽ですが他の検査法と比べると精度はやや劣ります
内視鏡を使う検査
内視鏡(胃カメラ)検査の際に、胃の組織を少し採取してピロリ菌を調べることもできます。顕微鏡で菌を直接見つけたり、菌の酵素活性を調べたり、培養して菌を増やしたりする方法があります。
内視鏡検査では、ピロリ菌の有無だけでなく、胃炎の程度や胃がんの有無も同時に調べることができるため、総合的な評価に適しています。
ピロリ菌の除菌治療
ピロリ菌の除菌治療は、胃カメラ検査で慢性胃炎や萎縮性胃炎など、ピロリ菌感染による変化が認められ、かつ、ピロリ菌の感染が確認された場合に、除菌治療の適応となります。除菌治療は外来で行うことができ、多くの方で菌を完全に退治することが可能です。
一次除菌
最初の除菌治療では、2種類の抗生物質(アモキシシリンとクラリスロマイシン)と胃酸を抑える薬の合計3種類の薬を、朝夕1日2回、7日間服用します。
薬の服用は決められた時間にきちんと飲むことが重要で、飲み忘れや途中でやめてしまうと除菌に失敗することがあります。除菌成功率は約80%です。
二次除菌
一次除菌で失敗した場合は、抗生物質の1つを別の薬(クラリスロマイシン→メトロニダゾール)に変更して再度除菌治療を行います。二次除菌の成功率は約95%以上と高く、ほとんどの方で除菌に成功します。
二次除菌でも失敗した場合は、三次除菌として別の抗生物質を使った治療も可能ですが、保険適用外となることがあります。
除菌治療の副作用
除菌治療中に現れる副作用として、下痢や軟便が最も多く、約10~20%の方に見られます。
その他の副作用として、味覚異常(苦味や金属の味がする)、腹痛、発疹、肝障害などが報告されていますが、多くは軽微で治療終了とともに改善します。
除菌治療の効果
ピロリ菌の除菌に成功すると、様々な良い効果が期待できます。最も重要なのは、胃がんの発生リスクを大幅に下げることです。なるべく若年のうちに除菌を行うことによって、より胃がんの発生リスクを下げることができます。
胃潰瘍や十二指腸潰瘍の再発もほぼ確実に防ぐことができます。従来は潰瘍の治療をしても再発を繰り返すことが多かったのですが、除菌により再発率を大幅に下げることができるようになりました。
慢性胃炎の進行も止めることができ、場合によっては胃炎が改善することもあります。ただし、すでに起こってしまった萎縮は完全には元に戻らないため、除菌後も定期的な検査は必要です。
除菌後の注意点
除菌治療が成功しても、いくつか注意すべき点があります。ピロリ菌の除菌によって胃の粘膜が修復されると胃酸の分泌が回復します。胃酸が増加することによって、胸やけやみぞおちの痛みなどの逆流性食道炎の症状がでやすくなります。症状の強さによって、胃酸の分泌を抑える薬を内服し症状を緩和します。
また、除菌後も定期的な胃がん検診(胃カメラ検査)を続けることです。除菌により胃がんのリスクは下がりますが、ゼロにはなりません。特に萎縮性胃炎が進んでいる方では、継続的な観察が必要です。
当クリニックでのピロリ菌の診療
当クリニックでは、ピロリ菌の検査から除菌治療、治療後の経過観察まで、一貫した医療を提供しています。
ピロリ菌感染が見つかり、胃カメラで萎縮性胃炎が確認された場合は、除菌治療の適応になります。除菌治療の必要性や方法について詳しくご説明します。
除菌治療中は、副作用への対応や服薬指導を丁寧に行い、患者さんが安心して治療を受けられるようサポートします。治療終了後は、除菌の成功を確認する検査を行い、結果に応じて今後の管理方針を決めます。
除菌成功後も、定期的な胃がん検診の重要性をお伝えし、適切な検査スケジュールをご提案いたします。また、胃の症状に変化があった場合の対応についても、いつでもご相談いただけるよう体制を整えています。